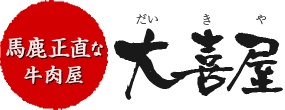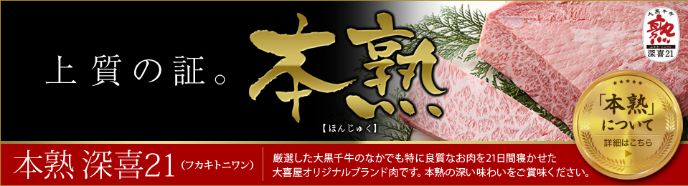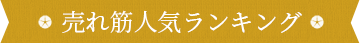男女ともに好きな鍋料理ランキングの上位に輝く「すき焼き」は、言わずと知れた伝統的な日本料理の1つです。年の瀬に親戚が集まったとき、お祝い事があったとき、そんな特別な日に家族みんなで鍋をつついたという思い出をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そんなすき焼きですが、実は地域によってその作り方や具材が異なります。そこで今回は、関東・関西のすき焼き事情をご紹介します。
関東風すき焼きは「割り下」が命

関東風のすき焼きにおける一番の特徴は、「割り下」の存在にあると言えるでしょう。割り下とは、しょう油・だし汁・みりん・砂糖などの調味料を混ぜて煮立てた汁のことを指します。割り下はすき焼きの味を左右する重要な役割を持っており、これが「店の味」「家庭の味」を決めると言っても過言ではありません。市販品も数多く販売されていますが、レシピを元に各家庭で割り下を作ることもできます。
関東風すき焼きを作る際にはあらかじめ調味料を計り、よく混ぜ合わせて割り下を準備しておきましょう。牛脂を溶かした鍋で肉を焼いたら割り下を流し入れ、これで具材を煮込んでいきます。
このように、関東では「すき焼き」という名前でありながら、具材を焼くのは最初の工程だけです。その理由は、関東圏におけるすき焼きのルーツが「牛鍋」だということに起因します。明治時代に牛肉を食べる文化を一気に広めるきっかけとなった牛鍋は、肉を焼くことなく、最初から割り下で煮込みます。牛鍋は外国人が多く居留していた横浜から広がり、その後東京で流行したことから、関東におけるすき焼き文化に影響を及ぼしたと考えられています。
関西風すき焼きは作る人の腕前が試される

割り下で煮込む関東風すき焼きに対し、関西風すき焼きは「焼く」というプロセスに重きが置かれています。関西風すき焼きも、まず牛脂を溶かした鍋で肉を焼く点は関東風と同じです。肉の両面に8割程度火が通ったら、肉の表面を覆うようにたっぷりと砂糖を振りかけます。さらにしょう油を回しかけ、上から白菜などの水気の多く出る野菜を投入してください。味の濃さは、煮詰まってきたら酒などを入れて調節すると良いでしょう。関西風すき焼きは関東風とは違い、水分が少なめな仕上がりになります。野菜の水分量は季節によっても異なるため、細かく味を見ながら調味料の量加減する必要があります。ここが鍋奉行の腕の見せどころです。関西風すき焼きは、作る人の腕前がすき焼きの出来栄えを大きく左右すると言えます。
東西の違いは作り方だけではない!具材にも特色あり

ここまで作り方に焦点を当てて東西の違いについて見てきましたが、実は東西の違いは作り方だけではありません。鍋に入れる肉以外の具材にも地域色は表れています。
例えば、すき焼きには長ねぎを入れることが一般的ですが、関西の家庭の中には「玉ねぎを入れることが当たり前!」という家庭もあります。すき焼きに玉ねぎを入れることで甘みが増し、味に深みが生まれます。
また、白菜も関西で好まれる具材です。先に説明した通り、関西風すき焼きには水気の多く出る野菜が欠かせません。水分を多く含む白菜は、味の調節にぴったりの具材と言えるでしょう。関東でも白菜を入れることはありますが、割り下で味の調節を行っている関東風すき焼きでは、水気の多く出る白菜を入れることで味が薄くなってしまうこともあります。関東風すき焼きに白菜を入れる場合は、味が薄くなることを考慮して割り下を作ることをおすすめします。
おわりに
一口に「すき焼き」と言っても、地域によってその作り方や具材にはばらつきがあります。皆さんが当たり前だと思って口にしていたそれぞれの家庭のすき焼きは、ところ違えば驚かれる一品かもしれません。たまにはお住まいの地域とは異なる地域のすき焼きを作ってみてはいかがでしょうか。